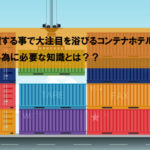ユニークな見た目が人気のコンテナハウス。ですが、コンテナハウスの魅力はビジュアルだけではありません。このページでは、建築物としてのコンテナハウスのメリットを様々な角度から解説していきます。
目次
コンテナハウスのデザイン面の魅力
コンテナハウスの特徴のひとつがビジュアルであることは間違いありません。コンテナハウスはカラー、素材、形、そのすべてにおいて独自の魅力を持っています。
- むきだしの鉄の質感
- 自由に選べるカラー
- ブロックのようなシルエット
むきだしの鉄の質感
コンテナハウスが目を引く理由はいくつかありますが、まずは鉄の質感です。むきだしの鉄でできた建物というのはなかなかありません。
鉄には経年劣化で愛着が湧くというメリットもあります。弊社CONTAINER WORKSのオフィス内にもインテリアの一環として鉄の波板を使用しています。鉄は木や他の様々な素材とも相性が良く、実は幅広いスタイルに取り入れやすい素材なのです。
自由に選べるカラー
コンテナハウスの外壁の色は、日塗工色見本の中から自由に選ぶことができます。鉄の質感を活かした無骨な雰囲気はもちろん大得意ですが、鮮やかなイエローやブルーで海外風に魅せることもできますし、スモーキーなアースカラーで柔らかいオシャレさを演出することも可能です。ここまで自由に見た目の印象を変えられるのは、コンテナハウスだからこそではないでしょうか。
ブロックのようなシルエット
コンテナハウスは鉄の箱のような見た目をしています。並べたり積み重ねたりすると、まるでブロックのよう。それ自体がデザインのアクセントとなるため「遊び心がある空間にしたい」ということであれば、コンテナハウスを取り入れるのがおすすめです。
コンテナハウスの機能面のメリット
コンテナハウスは機能の面でも他の建築物にはない魅力があります。
- いざとなったら移設できる
- 重量鉄骨造の中では安価で短納期
- 耐久性に優れている
いざとなったら移設できる
いざというときに、コンテナハウスは別の場所に移動することができます。簡単に・・というわけにはいきませんが、取り壊さずに、元の状態のまま移転することができるのはコンテナハウスの大きな強みです。
車台の上にコンテナを載せることで、基礎工事不要の「トレーラーハウス」として使用することもできます。近年では移動を念頭に入れたレスキューホテルや仮設住宅用のコンテナトレーラーの開発も進んでいます。
重量鉄骨造の中では安価で短納期
コンテナハウスは重量鉄骨造ですが、他の一般的な重量鉄骨造の建築物に比べると少し安いです。住み心地や住宅としての性能は変わりありませんから、デザインが気に入れば、自分らしい家を手にいれるための良い選択肢になるでしょう。
また、コンテナハウスはプレハブ工法で作るため、現地での施工期間が他の建築物よりも短く済みます。工場で組み立ててから現地に持ち込むため天候の影響を受けづらいのもポイントです。
耐久性に優れている
コンテナハウスは堅牢な建物です。コンテナハウスの元となっている海上輸送用コンテナは、多くの荷物を世界中に運ぶために、雨や風にも負けず、積み上げても壊れないよう頑丈である必要がありました。
建築用コンテナは、海上輸送用コンテナの堅牢性の上に建築基準法を満たした作りになっているため、非常に耐久性に優れています。
コンテナハウスで遊び心溢れる空間を
コンテナハウスは魅力がたくさん詰まった建築物です。用途によって、組み合わせ方や置き方、設備の付け方などカスタマイズの可能性は無限大。永く使っていく中で増設したり、塗りなおしたり、愛着を持って一緒に過ごしていけるのもコンテナハウスの魅力です。
コンテナハウスにご興味がおありのお客様は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。